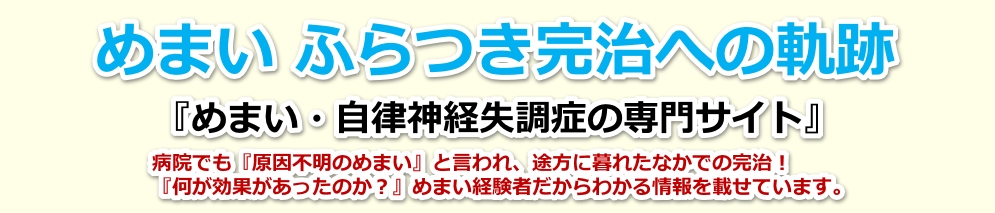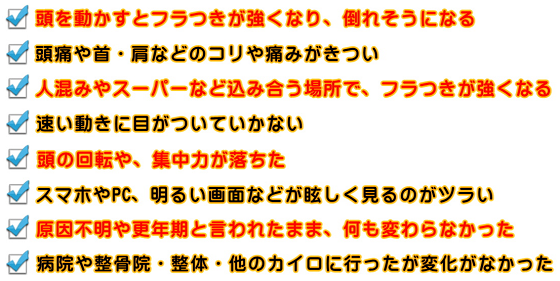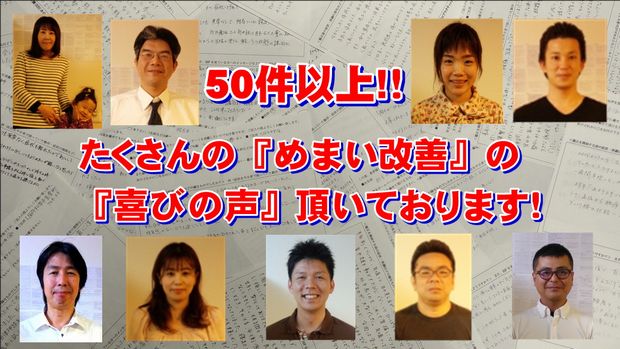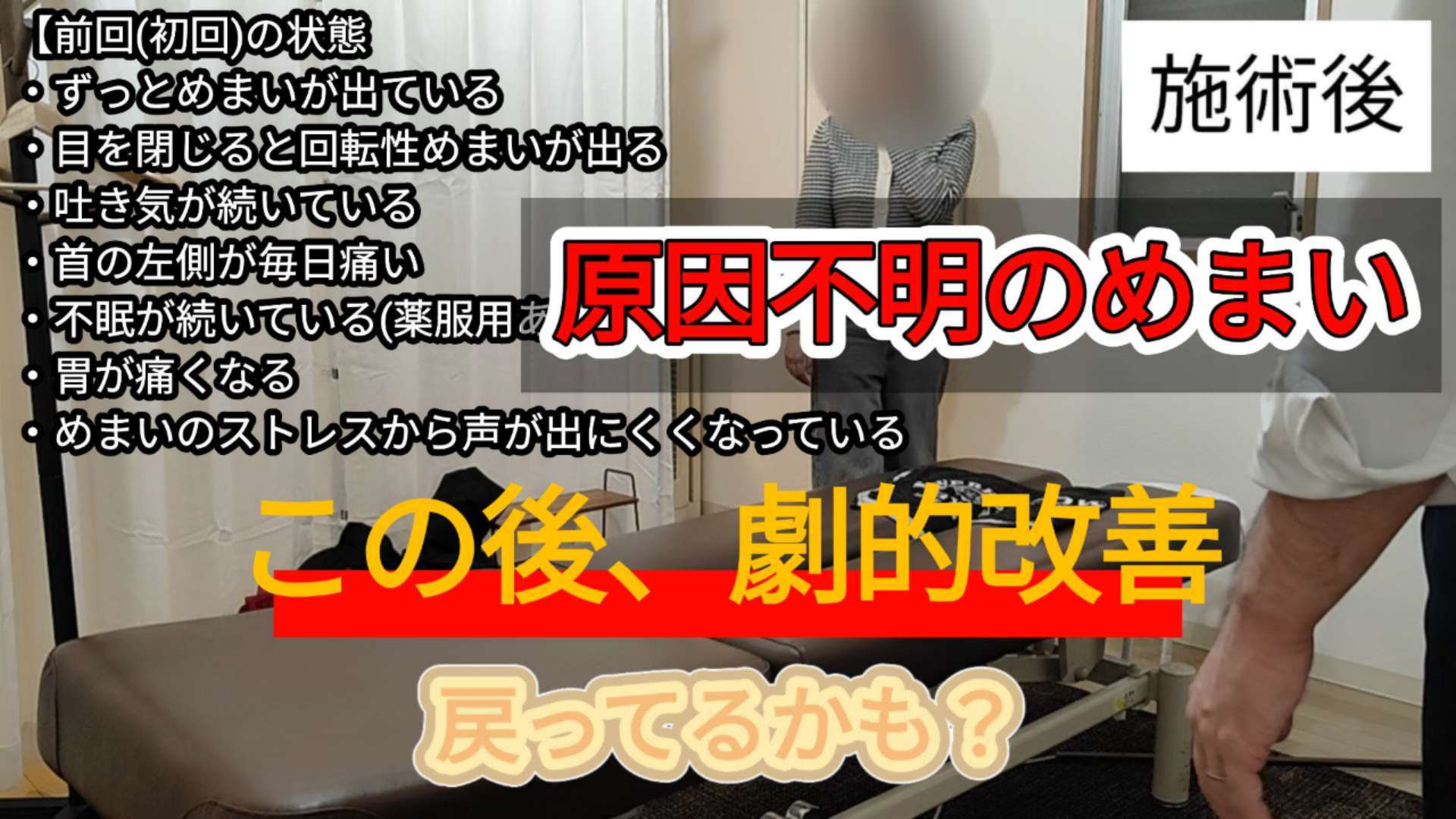耳管開放症の症状・原因・治療法・検査法・薬
■耳管開放症とは
耳管開放症は、耳と鼻をつなぐ「耳管(じかん)」が通常よりも開きすぎたり、閉じにくくなったりする状態を指します。
耳管は通常、耳の中の圧力を調整するために一時的に開きます(たとえば、あくびやつばを飲み込むとき)が、耳管開放症ではこれが異常に長く開いたままになることがあります。
■耳管開放症とめまいの関連性
めまいの方で「耳管開放症」と病院で診断されて様々な投薬治療を経験したが治らなくてお困りの方も多くいると思います。
私のクライアントさんでも、過去に耳管開放症と診断され、「ステロイド・イソバイド・漢方」など様々な薬を試して来たが改善せず数十年めまいに悩まされて来た。
当オフィスに通われ出しめまいが改善して来たある日、水分を摂る量が少なくなったらしく、耳管開放症の症状が出てまた酷くならないかすごく心配されていた。
耳に関係する複数箇所を確認すると強い変位を確認。
次の施術時に「いつも長引くのに、その日の夜には耳管開放症の症状が消えた!」と驚かれていた。
耳管開放症の原因は「ストレスや、脱水、ホルモンバランス、リンパ液、生まれつき」など、正直病院でも原因不明ですが、「耳鳴りや、耳の閉塞感、耳の中の痛み、突発性難聴」など耳の症状をめまいと共に訴える方は多く関連はあると思います。
長い突発性難聴の改善は難しい事が多いのですが、その他の耳の症状は改善する場合が多く、めまいと共に消えていきます。
だからといって、めまいは「耳」だけが原因ではないと思っています。
臨床上、複雑に原因が絡み合ってる方も多いので、様々な角度からアプローチする必要もあると思います。
症状
1.自分の声が大きく響く(自声強聴)
自分の声や呼吸音が耳の中で反響して大きく聞こえる。これは耳管が開いているため、声が直接耳に伝わりやすくなるからです。
2.耳の詰まり感や違和感
耳がふさがったような感じや圧迫感が続くことがあります。
3.耳鳴り
キーンという音や低音の響きが聞こえる場合があります。
4.聴力の変化
一時的に聞こえが悪くなったり、逆に過敏になったりすることがあります。
5.めまいやふらつき
耳管の異常が内耳の圧力に影響を与え、めまいを引き起こすことも。
6.その他
首を動かしたり、姿勢を変えたりすると症状が変化することがあります。
症状は人によって異なり、軽度で気づきにくい場合から日常生活に支障をきたす重度の場合まであります。
原因
耳管開放症が起こる原因は複数あり、以下のような要因が関係しています:
1.体重減少
急激なダイエットや病気による体重減少で、耳管周囲の脂肪組織が減少し、耳管が閉じにくくなることがあります。
2.ホルモンの変化
妊娠や生理、ホルモン治療による影響で耳管の機能が変化することがあります。
3.脱水症状
水分不足で粘膜が乾燥し、耳管の調整機能が低下することがあります。
4.解剖学的な異常
生まれつき耳管の構造が弱い、または狭い人がなりやすい場合があります。
5.ストレスや疲労
自律神経の乱れが耳管の開閉に影響を与えることがあります。
6.加齢
年齢を重ねると耳管周囲の筋肉や組織が弱くなり、症状が出やすくなることがあります。
7.その他の病気
アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、上気道感染などが間接的に影響を与えることも。
検査法
耳管開放症の診断には、耳鼻咽喉科での専門的な検査が必要です。主な検査方法は以下の通りです:
1.問診
症状の詳細(自声強聴や耳の詰まり感など)を医師に伝えます。症状が姿勢で変化するかどうかも重要な情報です。
2.耳鏡検査
耳の中を観察し、鼓膜の動きや異常がないかを確認します。
3.耳管機能検査
・チュービング法(耳管通気法): 鼻から空気を送り込んで耳管の開閉状態を調べる。
・ソノチュボメトリー: 音を使って耳管の開閉をリアルタイムで測定する。
4.鼓膜コンプライアンス検査(ティンパノメトリー)
鼓膜の動きを測定し、耳管が異常に開いているかどうかを確認します。
5.聴力検査
症状に伴う聴力低下がないかを調べます。
6.画像診断(必要に応じて)
CTやMRIで耳管周囲の構造的な異常を確認する場合もあります。
治療法
耳管開放症の治療は、症状の重さや原因に応じて異なります。以下に主な治療法を挙げます:
1.生活習慣の改善
・水分補給: 脱水を防ぐため、十分な水を摂取する。
・体重管理: 急激な体重減少を避け、適正体重を維持する。
・姿勢の工夫: 頭を下げたり横になると症状が軽減する場合があるので、日常生活で試してみる。
2.薬物療法
・鼻スプレーや点鼻薬: 粘膜の腫れを抑え、耳管の機能を調整する(例: 生理食塩水スプレー)。
・抗ヒスタミン薬: アレルギーが関与している場合に使用。
・ホルモン剤: ホルモン異常が原因の場合、医師の指導のもとで使用。
3.耳管通気療法
医師が専用の器具で耳管に空気を送り込み、正常な開閉を促す治療。症状の一時的な緩和に役立つことがあります。
4.手術
重症で他の治療が効果がない場合に検討されます。
耳管ピニング: 耳管に物質(例: コラーゲンや脂肪)を注入し、開きすぎを防ぐ。
耳管閉鎖術: 耳管を部分的に閉じる手術。ただし、リスクもあるため慎重に判断されます。
5.リハビリテーション
耳管の筋肉を鍛えるための運動(例: つばを飲み込む動作を意識的に行う)が推奨されることもあります。
耳管開放症に対する薬物療法
耳管開放症の薬物療法は、耳管の異常な開きを直接閉じる薬は存在しないため、以下の目的で処方されます。
・耳管周囲の粘膜の状態を整える
・炎症やアレルギーを抑える
・自律神経を調整する
・症状(自声強聴や耳鳴りなど)を軽減する
治療は耳鼻咽喉科医の診断に基づいて行われ、原因や症状に応じて薬が選ばれます。
主な薬の種類と具体例
1.生理食塩水スプレーや点鼻薬(粘膜の保湿・調整)
・役割: 耳管や鼻腔の粘膜を潤し、乾燥による耳管の開きすぎを防ぐ。
・具体例:生理食塩水ベースの鼻スプレー(市販品では「オトリビン」や「ナザール」のようなもの。ただし、血管収縮剤が入っていないものを選ぶ)
医師が処方する保湿用の点鼻液
使用場面: 脱水や乾燥が原因で症状が悪化する場合に有効。
特徴: 副作用が少なく、日常的に使いやすい。
2.抗ヒスタミン薬(アレルギー対策)
・役割: アレルギー性鼻炎や鼻づまりが耳管に影響を与えている場合に、粘膜の腫れや分泌を抑える。
・具体例:
セチリジン(商品名: ジルテック)
ロラタジン(商品名: クラリチン)
フェキソフェナジン(商品名: アレグラ)
・使用場面: アレルギーが関与している場合。
・特徴: 眠気が出る場合があるので、第二世代(眠くなりにくいタイプ)がよく使われる。
3.ステロイド点鼻薬(炎症抑制)
・役割: 鼻腔や耳管周囲の炎症を抑え、耳管の機能を正常化する。
・具体例:
ブデソニド(商品名: フルナーゼ)
モメタゾン(商品名: ナゾネックス)
・使用場面: 副鼻腔炎や慢性的な鼻炎が背景にある場合。
・特徴: 短期間の使用が一般的で、医師の管理が必要。
4.血管収縮剤(一時的な緩和)
・役割: 鼻粘膜の腫れを一時的に抑え、耳管の圧力を調整する。
・具体例:
オキシメタゾリン(市販の鼻スプレーに含まれることが多い)
・使用場面: 急性の症状緩和が必要な場合。
注意点: 長期使用は「リバウンド現象」(症状が悪化する)を引き起こす可能性があるため、数日以内の使用に限る。
5.ホルモン剤(ホルモン異常の調整)
・役割: 妊娠やホルモンバランスの乱れが原因の場合に、耳管周囲の組織を安定させる。
・具体例:
エストロゲン含有薬(医師の判断で処方)
・使用場面: ホルモン変動が関与している稀なケース。
・特徴: 専門医による厳密な管理が必要。
6.自律神経調整薬(ストレス対策)
・役割: 自律神経の乱れが耳管の開閉に影響を与えている場合に使用。
・具体例:
軽い鎮静剤や抗不安薬(例: エチゾラム)
・漢方薬(例: 加味逍遥散、半夏厚朴湯)
・使用場面: ストレスや疲労が背景にある場合。
・特徴: 症状が精神的な要因と関連しているときに補助的に使用。
7.その他(症状緩和のための対症療法)
・耳鳴り対策: ビタミンB12や血流改善薬(例: メチコバール)
・めまい対策: 抗めまい薬(例: ベタヒスチン)
薬物療法の限界と注意点
効果の限界: 耳管開放症の根本的な治療薬はなく、あくまで症状を和らげる補助的な役割です。薬だけで完治することは少ないです。
副作用: 薬によっては眠気、口の渇き、鼻の乾燥などの副作用が出る可能性があります。
医師の指導: 市販薬を使う場合も、長期間の使用は避け、耳鼻咽喉科で相談するのが安全です。
補足: 非薬物療法との併用
薬物療法は、生活習慣の改善(水分補給、体重管理)や耳管通気療法、手術(重症の場合)と組み合わせることで効果が高まります。たとえば、生理食塩水スプレーを使いながら十分な水分を摂取するだけでも、軽症の場合は改善が見られることがあります。
●頭痛や首・肩などのコリや痛みがきつい
●人混みやスーパーなど、込み合う場所で、ふらつきが強くなる
●速い動きに目がついていかない
●頭の回転や、集中力が落ちた
●スマホやパソコン、明るい画面や空などが眩しく見るのがツラい
●原因不明や更年期、自律神経失調症などと言われたまま、何も変わらなかった
●病院や整骨院・整体・他のカイロに行ったが変化がなかった
この様な方は諦めずに、私にご相談下さい。
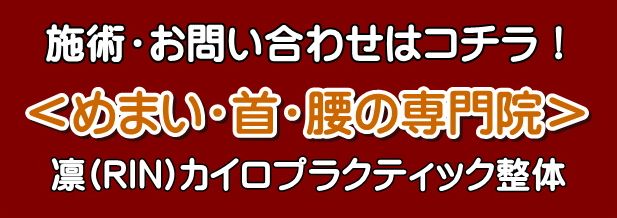
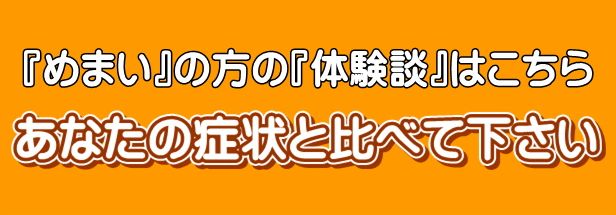
●トップページへ戻る